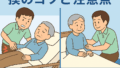「利用者ファーストだから…」って、その先に誰が残る?
介護現場で当たり前のように使われる言葉。
「利用者の希望を第一に」
「クレームが出ないように丁寧に」
「臨機応変に応えてあげて」
もちろん、利用者目線は大切。
でも、それを現場スタッフの“無理”で支えてる構造、いつまで続けるつもり?
優しさで成り立ってる職場は、崩れやすい
- ケアプランにない「ついでの掃除」や「延長」 「断ったら苦情になる」と我慢
- サ責が波風立てたくなくて、何も言わない 「ここまでやるのが普通やろ?」の空気が蔓延
一見、親切で良さそうに見える。
でも、それを“支える人”が壊れていくのが問題
利用者の希望を叶えることが目的になってないか?
- できることまで全部やってしまう
- 過剰に気を遣いすぎて本音が言えない
- 家族の希望が“介護内容”を決めてしまう
…それ、本当に本人のための介護?
壊れるのは、スタッフ → 介護サービス → 利用者
現場のスタッフが疲弊し、離職が増えて人が足りなくなると、結局はそのツケが利用者に返ってくる。
最初は良かれと思ってやってたことが、
結果的に**「誰も守れない介護」**になってしまう。
本当に大切なのは「介護士ファースト」
バルクケアの考えはこう。
介護士ファーストこそが、本物の利用者ファーストにつながる。
- スタッフが余裕を持って働けるからこそ、ちゃんと笑って向き合える。
- 断るべきことをはっきり伝えられる勇気も生まれる。
そして、本当に必要なケアに集中できる。
バルクケアの結論
「利用者ファースト」が行き過ぎると、現場が壊れて、結果的に利用者すら守れなくなる。
まず守るべきは、現場で支えている介護士。
だから、介護士ファースト
それが一番“利用者に優しい”介護やと思います。