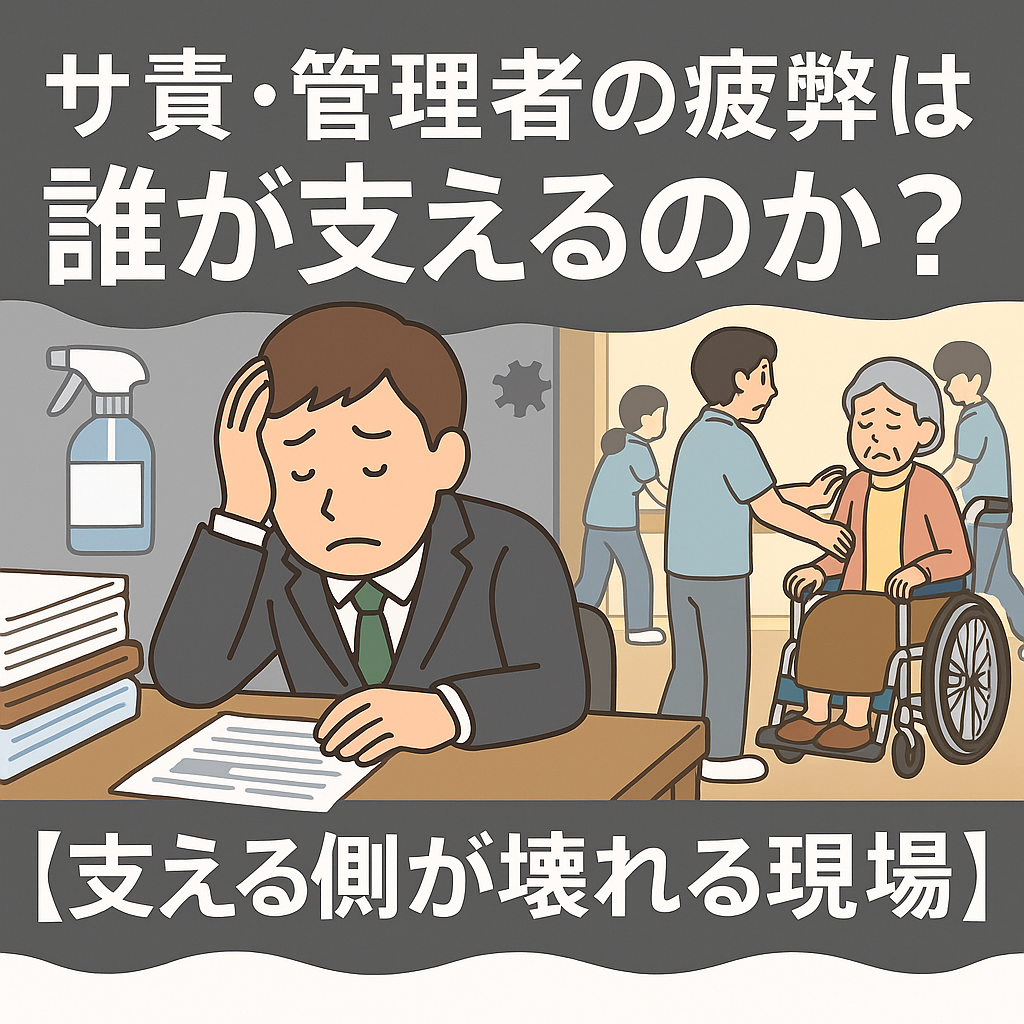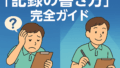はじめに
「何かあればサ責が対応してくれる」
「トラブルが起きたら、管理者に相談すればいい」
「現場がうまく回っているのは、あの人が頑張ってくれているから」
そんなふうに見える職場の裏側で、
支える立場の人たちが、静かに壊れていく現場が増えています。
利用者やスタッフの“受け皿”として動き続けるサ責・管理者。
でもその彼らを、誰が支えているのでしょうか?
サ責や管理者が抱える見えないプレッシャー
- スタッフの出勤状況やシフト管理
- 苦情対応,事故報告,行政,ケアマネ対応
- 利用者,家族からの急な要望
- 現場の人間関係の調整
- 上司からの数字や経営的なプレッシャー
目の前の業務だけでなく、
“板挟み”の中で全方位に気を配る仕事を担っているのがサ責・管理者です。
「何でもできるから任せられる」の罠
真面目で責任感が強く、柔軟に動ける人ほど、
現場で“便利屋”のような存在になってしまいがちです。
- スタッフが対応しきれない業務を無言でフォロー
- 苦情の矢面に立つ
- 指導とサポートを同時にこなす
- 残業してでも現場を整える
その頑張りは評価されます。
でも、「あの人ならできる」が積み重なった結果、
その人にしか回せない現場になってしまうのです。
限界を迎えてからでは遅い
サ責・管理者が疲弊している兆候は、なかなか外から見えにくいもの。
なぜなら、彼ら自身が**“弱音を吐けない立場”**であることが多いからです。
- 「自分がしんどいと言ったら、スタッフに迷惑がかかる」
- 「現場の空気が悪くなるから、愚痴は言わないようにしている」
- 「今抜けたら誰が対応するのか分からない」
そんなふうに耐え続けた結果、
体調を崩したり、突然退職してしまうことも珍しくありません。
支える人を支えるために必要な視点
1人のリーダーに負担が集中する構造は、
本人だけでなく、現場全体にとっても大きなリスクです。
以下のような対策・意識が必要です。
サ責や管理者も「一人の人間」
現場が円滑に動いていると、
リーダー層が“機械のように働いてくれている”ように錯覚しがちです。
でも実際には、
彼らも疲れるし、悩むし、落ち込むこともある一人の人間です。
- 感情的なクレームに傷つくこともある
- 自分の判断で職員を苦しめてしまったかもしれないと悩む
- 「このやり方で本当に良かったのか」と葛藤を抱えている
それでも前に進もうとしている人を、
“できて当たり前”にしてはいけません。
おわりに
支える側が壊れてしまったら、
その影響は、現場全体、ひいては利用者にも広がっていきます。
だからこそ必要なのは、
サ責・管理者という立場を「支える」という発想です。
- 頑張っていることに気づいて声をかける
- 負担を減らす工夫を現場全体で考える
- 一人に背負わせない体制をつくる
サ責や管理者が、ずっと元気に働けること。
それが、介護現場の“持続可能性”に直結します。