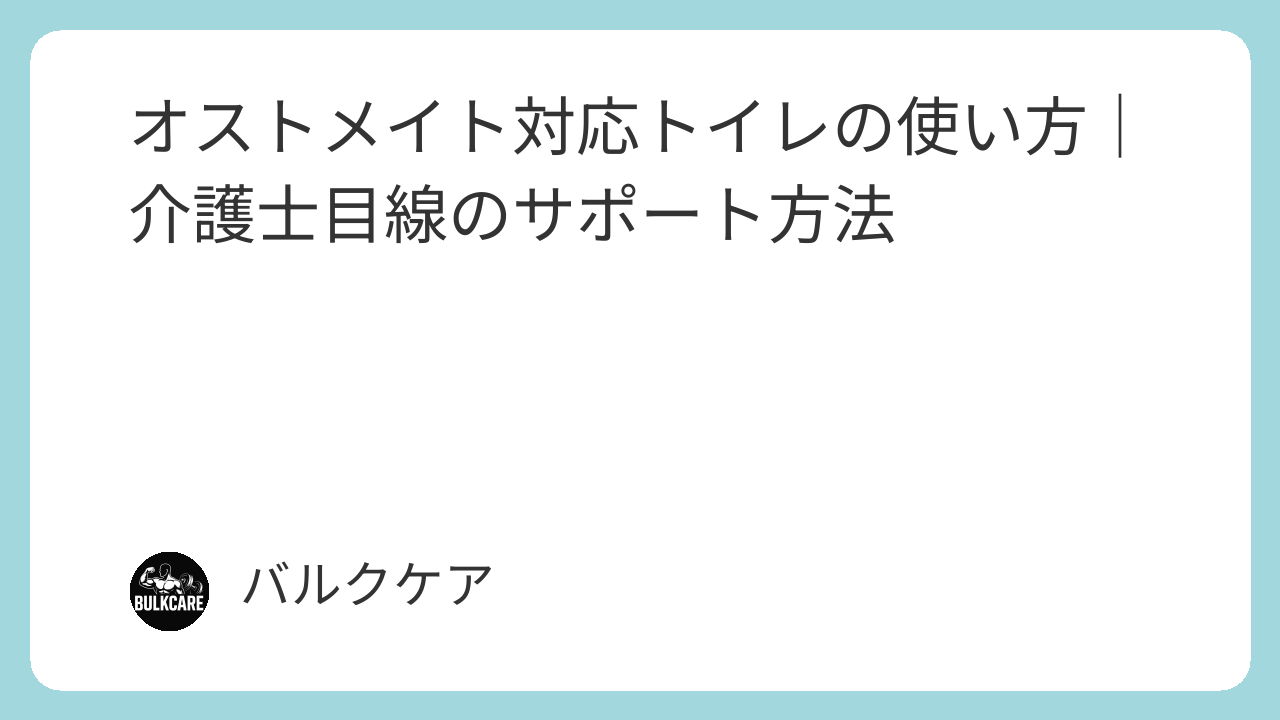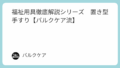はじめに
オストメイト対応トイレは、人工肛門や人工膀胱を造設している方が、安心して排泄やケアを行うために欠かせない設備です。
でも実際に介護士として同行したとき、「どうサポートすればいいの?」と迷う人も多いはず。
今回は、バルクケア流に介護士目線でのサポートの流れを解説します。
事前に確認しておきたいこと
外出支援や通院の付き添いで大切なのは「下調べ」。
目的地の施設にオストメイト対応トイレがあるか 設備の種類(シャワー水栓あり / 前広便座あり など) 利用しやすい場所にあるか
これを把握しておくと、利用者さんも安心して外出できます。
利用者さんの自立度を尊重する
オストメイトのケアは、とてもプライベートな領域。
介護士としては「すべて手伝う」よりも、どこまで自己処理できるかを尊重する姿勢が大切です。
自分で処理できる方 → 近くで見守り、必要時に声をかける 一部だけ介助が必要な方 → パウチの洗浄や物品準備を補助 全介助が必要な方 → 本人の尊厳を守りながら声かけを徹底
実際のサポートの流れ
① 声かけして安心感を与える
「ゆっくりで大丈夫ですよ」など、焦らせない言葉がポイント。
② 便座や洗浄機能を調整
前広便座や水栓の使い方を一緒に確認。
③ 物品の準備を補助
パウチ交換用の袋やティッシュをそろえておく。
④ 処理中はプライバシーを尊重
必要以上に見ず、できるだけ利用者さんに任せる。
⑤ 終了後の後片付けをサポート
ゴミ袋の処理や消臭スプレーなどをサッと行う。
介護士が注意したいポイント
焦って急かさない 設備に不慣れな利用者さんには丁寧に説明 ニオイや汚れが気になっても表情に出さない 清潔保持と感染予防を徹底する
オストメイトケアは、体力よりも心の筋力が試される場面です。
バルクケア流まとめ
オストメイト対応トイレを使うときに大切なのは、設備の知識と「尊重の姿勢」。
介護士が焦らずサポートすることで、利用者さんの自立と安心を守ることができます。
「筋肉は力を支える。声かけと尊重は心を支える」
これがバルクケア流・オストメイトサポート術です。