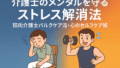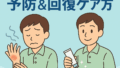こんにちは、バルクケアです!
現在介護・福祉の現場経験10年以上。
現場で培った「実際に役立つ福祉用具の知識」を筋肉視点も交えてお届けします。
今回は介護現場でも在宅介護でも必須アイテム、車いすについて徹底解説します。
「なんとなく選んでしまったけど、思ったより使いにくい…」
「利用者さんが疲れやすくて長時間乗れない…」
そんな悩みは、正しい選び方と使い方でほぼ解決できます。
車いすの基本構造と種類
車いすは大きく分けて次の2タイプがあります。
① 自走式
• 利用者自身がハンドリム(車輪の外側についている輪)をこいで移動するタイプ
• 後輪が大きく、自分で操作できる
• 自立支援やリハビリに向いている
② 介助式
• 後輪が小さく、ハンドリムがない
• 介助者が押して移動する前提
• 狭い室内や病院など短距離移動に向く
これに加えて、リクライニング式・ティルト式などの特殊タイプもあります。
• リクライニング式:背もたれを倒して休憩や体位変換が可能
• ティルト式:座面ごと角度を変えられ、姿勢保持や褥瘡予防に有効
車いす選びで失敗しないための3つのポイント
① 利用者の身体状況を最優先
• 上肢の筋力がある → 自走式
• 腕力が弱い・自走が難しい → 介助式
• 姿勢保持が困難 → ティルト・リクライニング式
② 使用環境を考慮
• 外出メイン → 空気タイヤ(クッション性◎)
• 室内メイン → ノーパンクタイヤ(メンテ不要)
• 段差やスロープが多い環境 → 大径タイヤで安定性確保
③ 座面サイズとクッション性
• 幅は「お尻の幅+2cm」が目安
• 座面高は「足の裏がしっかり床(またはフットサポート)に着く高さ」
• クッションは褥瘡予防タイプを選ぶと長時間でも快適
バルクケア流!快適&安全な活用術
① 体幹サポートで疲れ知らず
座位姿勢が崩れると腰痛・肩こり・疲労が増えます。
介護現場ではランバーサポート(腰クッション)やサイドサポートを追加し、骨盤を立てる姿勢をキープ。
元自衛官的視点で言うと「姿勢は戦闘力」。姿勢が安定すると活動時間も長くなります。
② ブレーキの習慣化
介助者は「止まったらブレーキ」を徹底。
これは筋トレでいうフォーム固定と同じで、安全確保の基本です。
③ 段差・傾斜の攻略法
車いすで段差を乗り越える時は、介助者は膝を曲げて腰を落とし、テコの原理で前輪を持ち上げる。
元自衛官の私からすると、これは“荷物搬送訓練”の応用です。
実際の現場であった「失敗」と「改善」
ある利用者さんは、座面幅が広すぎる車いすを使用しており、体が左右に傾いていました。
結果、長時間の外出で腰痛が悪化。
→ 改善策:ジャストサイズの車いす+ランバーサポートで姿勢が安定。外出時間が倍になった。
まとめ
• 車いす選びは「身体状況」「使用環境」「サイズ・クッション性」の3要素が重要
• バルクケア流は姿勢保持+安全習慣+介助者の腰守りがテーマ
• 適切な車いすは、利用者の活動の幅を広げ、介助者の負担も減らす