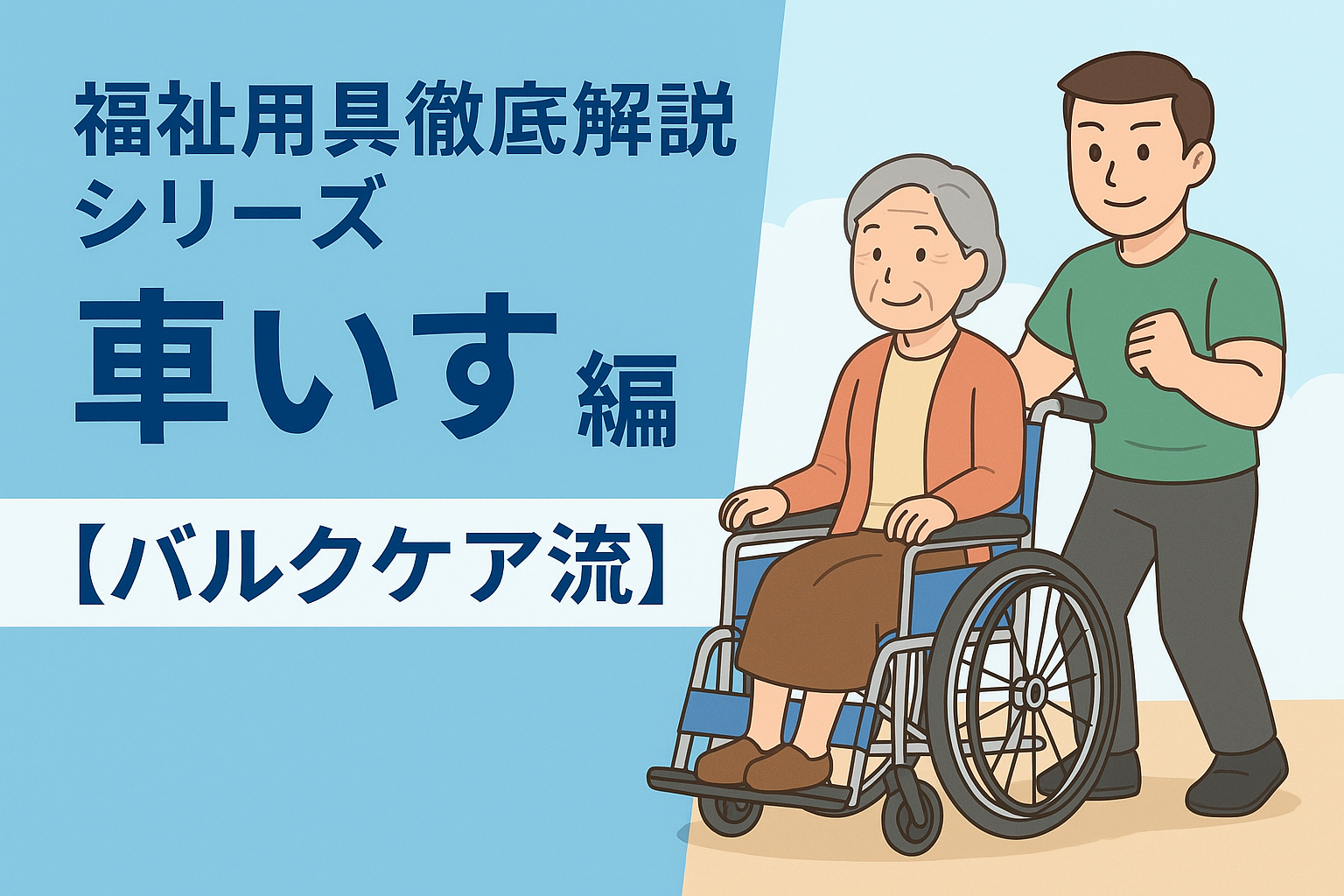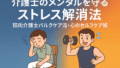こんにちは、バルクケアです。
今回は 福祉用具徹底解説シリーズ として、介護現場で欠かせない 「車いす」 をテーマにお届けします。
僕はこれまで 介護福祉士・福祉用具専門相談員 として多くの車いすを扱ってきました。
そして元自衛官で筋トレ好きという立場から、ただの機器説明だけでなく「現場でどう使いやすくするか」まで掘り下げます。
車いすの種類と選び方
車いすは大きく分けて以下の3タイプがあります。
1. 自走式
利用者自身が大きな後輪をこいで移動できるタイプ。
→ 腕力や持久力がある方に適しており、リハビリにもなる。
2. 介助式
小さな後輪で、介助者が押して移動するタイプ。
→ 高齢者や筋力が弱い方、狭い通路の多い家屋に向いている。
3. 多機能型(リクライニング・ティルト)
背もたれや座面の角度が変わるタイプ。
→ 長時間座位が困難な方や、褥瘡予防が必要な方に有効。
バルクケア流「快適セッティング術」
介護現場でよくあるミスは、車いすのサイズや設定が合っていないことです。
快適に使うためには以下のポイントを押さえましょう。
• 座面高さ:足裏がしっかり床につく高さに調整(低すぎると膝関節に負担)
• 座幅:体にフィットする幅(広すぎると姿勢が崩れる)
• クッション:褥瘡予防と座り心地改善のため必須
• ブレーキ位置:利用者or介助者が確実に操作しやすい位置
車いすを安全に使うコツ
• 段差は前輪を軽く上げて通過(元自衛官時代の搬送スキルが役立ちます)
• ブレーキは移乗時に必ずロック(現場では意外と忘れられがち)
• 足置きは移乗時に必ず跳ね上げ(つまずき事故防止)
筋トレ好き介護士からのアドバイス
車いす介助は意外と全身運動です。
押す時は腕だけでなく脚と体幹を使って押すと腰の負担が減ります。
僕はスクワットやデッドリフトのフォームを応用して、長時間でも疲れにくい介助をしています。
まとめ
• 車いすは「種類・サイズ・調整」が命
• クッションやブレーキ位置の最適化で利用者の快適度アップ
• 介助者は筋トレ知識を活かして体を守ろう!