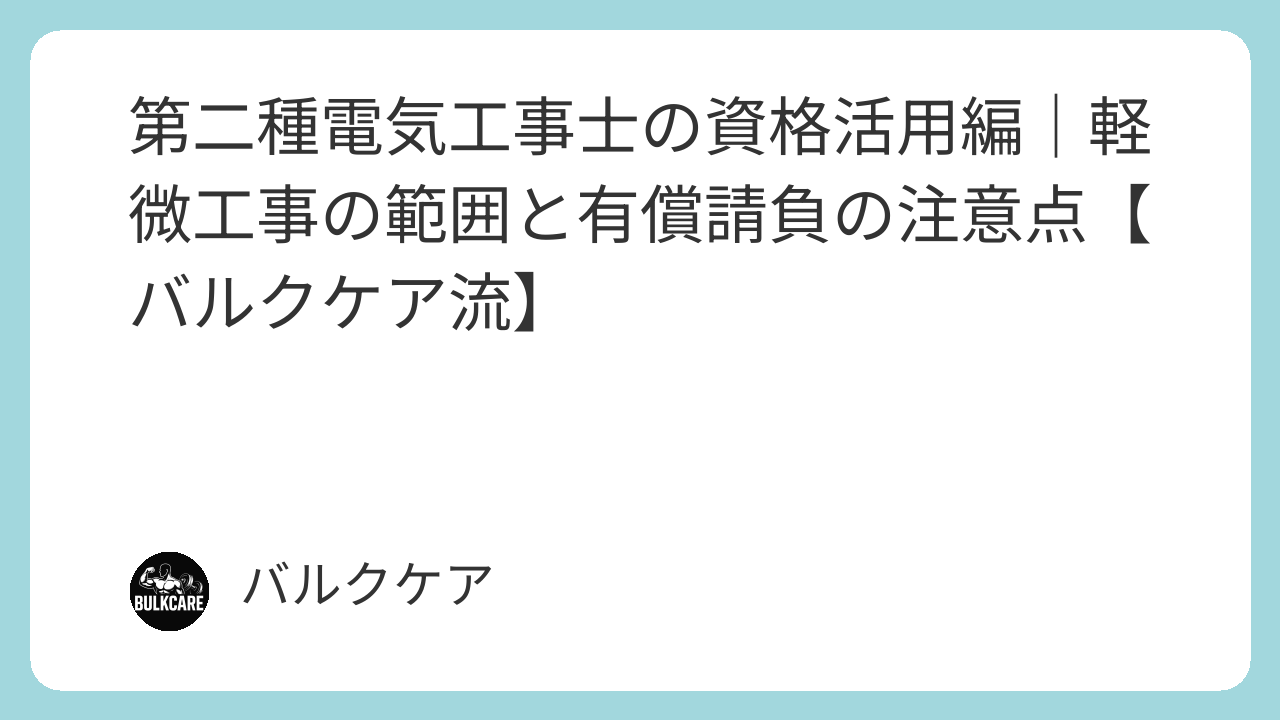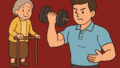こんにちは、バルクケアです!
今回は第二種電気工事士を取得した後、実際にどう活かすのか、そして注意すべき法律面を解説します。
資格を取ったら「すぐ仕事にできる!」と思いがちですが、実はルールがあります。
軽微な工事の範囲
第二種電気工事士の資格を持っていても、すべての工事が自由にできるわけではありません。
法律上「軽微な工事」と呼ばれる範囲なら、登録なしで行えます。
代表的な軽微工事は…
コンセントやスイッチのカバー交換(配線に触れない) 電圧600V以下の差し込みプラグやコンセントの接続 照明器具の取り付け(配線工事を伴わない) 電球や蛍光灯の交換
これらはDIYレベルでも行われていますが、安全に行えるのは資格を持つ人の強みです。
有償で請け負う場合の注意点
資格を持っていても、継続的に有償で工事を請け負う場合は
電気工事業の登録(都道府県) 規模によっては建設業許可 が必要になります。
たとえば…
「コンセント交換1件3,000円」で毎月複数件やる 定期契約で施設や店舗の工事を請け負う こういった場合は、軽微工事でも“業”とみなされ、無登録営業のリスクがあります。
安全な活用パターン(バルクケア流)
自宅や家族、友人宅での無償作業 → 基本的にOK(ただし安全責任あり) 勤め先施設の業務の一環として → 会社の許可があればOK 副業としてやる場合 → 登録を済ませておくと安心
僕はこの資格を持っていることで、介護施設のちょっとした電気トラブルを即解決できるようになりました。
そのおかげで「頼れる存在」として評価もUP。資格は現場力を底上げしてくれます。
まとめ
第二種電気工事士は、生活にも仕事にも役立つ万能資格。
でも有償で工事を請け負うなら、必ず法律面もチェックしましょう。
正しい知識と資格を組み合わせれば、あなたの価値はもっと高まります。
これは筋トレで言えば「正しいフォームで重量を上げる」のと同じ。安全と効率、両方を狙っていきましょう。