こんにちは、バルクケアです。
介護の現場で必要なのは、筋肉と同じくらいコミュニケーション力です。
ベンチプレスで100kg上げても、ご利用者様の心を持ち上げられなかったら意味がありません。
今日は、介護と筋トレ、両方から学んだ「現場で使えるコミュニケーション術」をご紹介します。
「聴く力」は筋トレでいうフォーム作り
筋トレでフォームが崩れるとケガするように、会話も聞き方が雑だと信頼が崩れます。
ご利用者様が話すことを、ただ耳で聞くのではなく、表情・声のトーン・仕草まで観察。
スクワットで鏡を見るように、「全体を見て」相手の本音をキャッチしましょう。
名前を呼ぶのは「声のアップ」
トレーニング前にウォームアップをするように、会話にもウォームアップがあります。
それが「名前を呼ぶこと」。
「〇〇さん、おはようございます!」と一声かけるだけで、距離がぐっと縮まります。
これは現場で即効性のある“声のストレッチ”です。
ネガティブワードは重量オーバー
筋トレで重量を無理に増やすとケガするように、
「無理」「できません」という言葉は相手の心に負荷をかけすぎます。
代わりに「こうすればできますよ」「一緒にやってみましょう」という軽めのポジティブワードを使いましょう。
これで相手のやる気が自然とアップします。
ユーモアは現場のプロテイン
現場がピリピリしているときほど、笑顔と冗談は栄養になります。
ただし、プロテインも味を間違えるとまずいように、冗談も相手の好みに合わせるのが鉄則。
「この持ち上げ方はデッドリフトですね!」なんて筋トレネタで笑ってくれる方も意外と多いです。
チーム共有は“セット間の休憩”
筋トレは休憩の取り方で次のセットのパフォーマンスが変わります。
介護も同じで、情報共有がスムーズだと次のケアがうまくいく。
「この前〇〇さん、こんなこと話してましたよ」と小さな情報もシェアすることが、現場の“筋力”を高めます。
まとめ
介護のコミュニケーションは、筋トレと同じで「日々の積み重ね」が大事です。
フォーム(聴き方)を整え、ウォームアップ(名前呼び)で距離を縮め、適切な重量(言葉)で相手を支える。
これを意識すれば、現場の雰囲気は確実に良くなります。
筋肉も信頼関係も、一朝一夕では作れません。
でも、毎日少しずつ鍛えれば、必ず強くなります。
さあ今日も、心と体、両方を鍛えていきましょう!

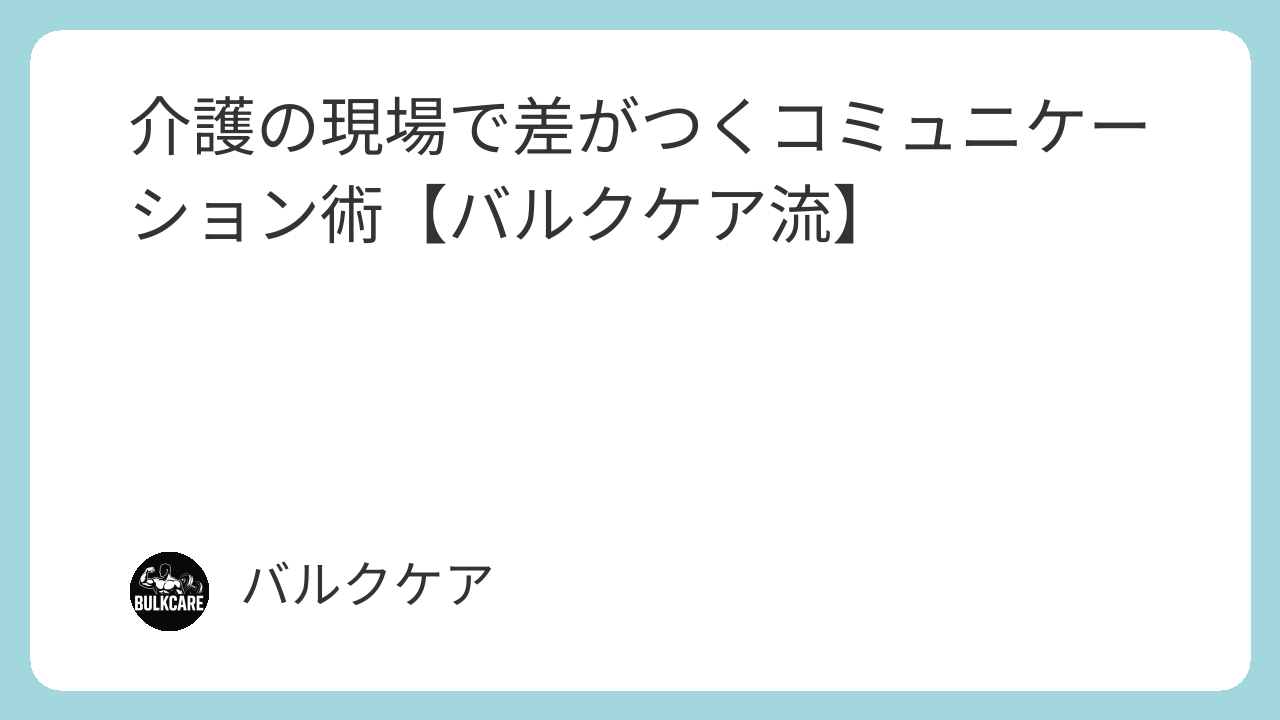
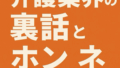

コメント